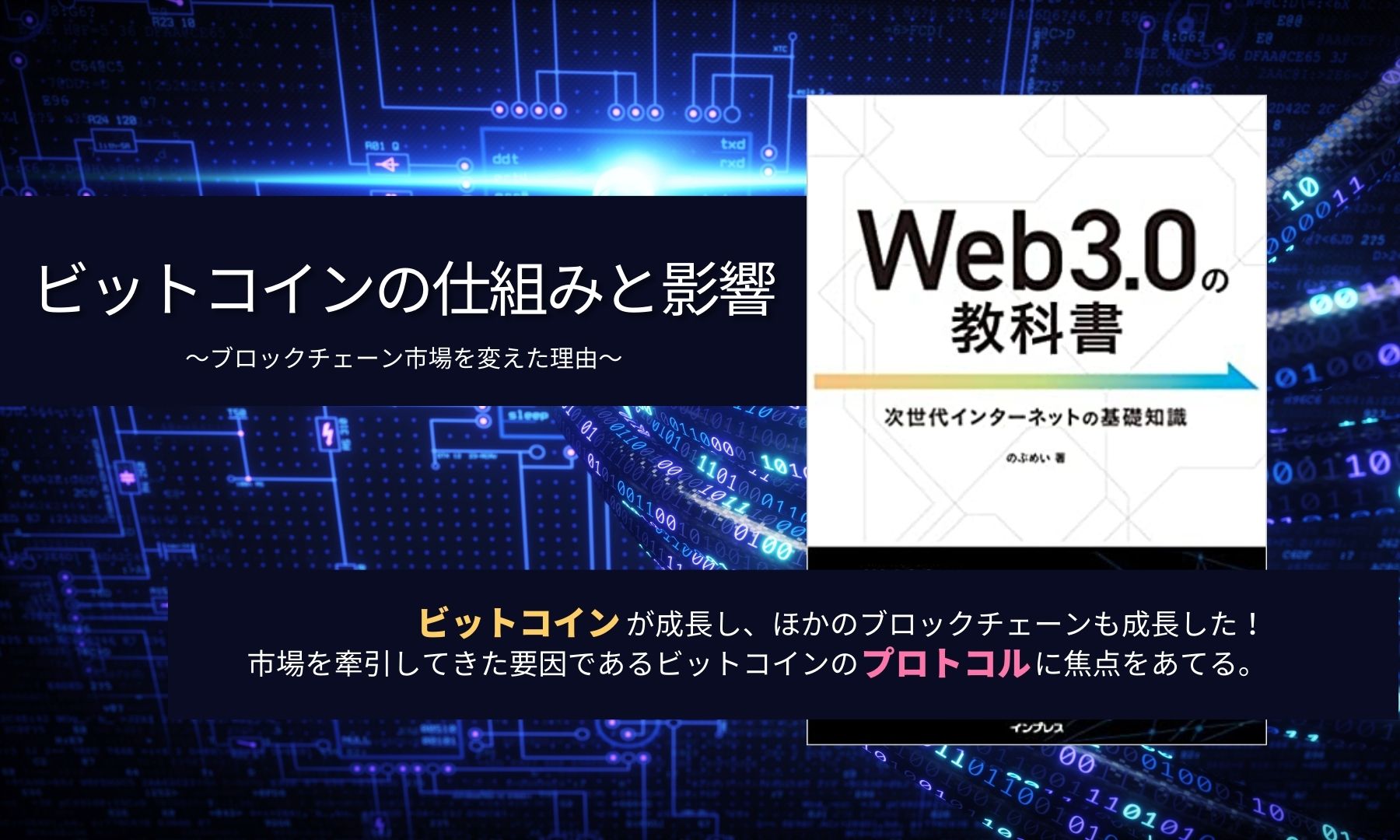ブロックチェーン市場を牽引するビットコイン
前記事では、ブロックチェーン市場の市場規模が2兆ドルを突破し、インターネット市場に比べて5倍速く成長していることを説明しました。ここでは、その成長を牽引するビットコインについて解説していきます。
1.ブロックチェーン市場の成長
本質が見えづらいブロックチェーン
ブロックチェーン市場における時価総額トップ30銘柄の市場シェア率(2021年末)を見ると、BTCがトップになっています。BTCのシェアは2021年初頭で7割、年末にかけて徐々に減少しましたが、それでも5割を占めています。
出典:CoinGecko「Yearly Report 2021 - 2021 年 トップ30 銘柄シェア」をもとに作成
市場全体におけるBTCの影響力は大きく、2兆ドルの巨大な市場は、BTCが牽引して成長したといえるでしょう。そして、BTCのシェア率は徐々に落ちつつあり、ビットコインを入り口として入ってきた資産が、次点でのシェア率を誇るイーサリアムなど、ほかのブロックチェーンに流出しているというのが現在のトレンドです。
ビットコインが成長し、市場規模が拡大するにつれ、関わる人が増え、ほかのブロックチェーンも成長した、という経緯です。そこで、ビットコインがここまで成長した要因を探るために、ビットコインのプロトコル(共通のルール)を見ていきましょう。
2.ビットコインの基本プロトコル
プロトコルと「BTC」「ビットコイン」の使い分け
「プロトコル」とは共通のルールのことです。インターネットはTCP/IPやWWWといった世界共通のルールがあるからこそ、世界中の人々が利用できます。ここでは、プロトコルを「世界共通で不変のルール」という意味で使います。また本記事では、「BTC」と「ビットコイン」の表記を意識して使い分けています。一般的にBTCは通貨そのものを指し、ビットコインはBTCを形成するネットワークや仕組みなどのことを指します。ここからビットコインのプロトコルについて説明していきます。
ビットコインが生み出したブロックチェーン技術
ブロックチェーンが拓く未来:所有権を証明する技術の真髄では「ブロックチェーン技術により、デジタルデータに希少性が生まれ、希少性の高いデータに資産価値が認められ始めた。その代表例がBTC」と説明しました。BTCの発行枚数は2,100万枚と決められており、1枚ずつの所有者が明らかなので、勝手に模造品をつくることが難しく、改ざんできません。所有を証明するだけではなく、証明した結果を改ざんできない仕組みにしている点がブロックチェーンの特徴です。このような特徴をプログラムとして書き込み、改ざんできない状態で、世界共通で不変のプロトコルとしたことが革新的なのです。それでは、どうやって改ざんできない仕組みを実現しているのかを、次に見ていきます。
3.改ざんできない仕組みを実現する技術
ブロックチェーン技術は、複数の既存の技術の組み合わせでできています。代表的なものが次のものです。順を追って説明していきます。
① 暗号化技術
メールや大事な情報などを送る際に、データを保護し、安全に通信するための技術
② P2P通信
データを送り合うユーザー同士が直接やり取りする通信方法
③ 分散型台帳技術
データを分散して管理する技術。DLT(Distributed Ledger Technology)ともいう
④ コンセンサス・アルゴリズム
コンセンサス(合意)形成を行うための仕組みやルール
① 暗号化技術
ビットコインは、楕円曲線暗号方式により、個人の持つ秘密鍵から公開鍵を生成し、匿名者間での通信を行っています。難しい仕組みはおいておき、ここで行っているやり取りをシンプルに描いたものが下図です。
AさんからBさんへの「1BTC送金」の記録をブロックに詰め、BさんからCさんへの「1BTC送金」の記録を次のブロックに詰め、それらを繰り返して時系列順に並べることで、「Aさんが持っていたBTCを今、誰が持っているのか」を確認できます。ビットコイン上の送金を可視化する「chainFlyer(チェーンフライヤー)」などのツールでは、今、誰かがBTCを送金してブロックを生成している様子を見られます。
このとき、誰かが途中で送金記録を改ざんすると、どこかで帳尻が合わなくなります。この「時系列順に」という点がポイントで、帳尻が合わなくなった際、「どこで改ざんされたのか」をさかのぼって検証できるようになっています。
この「ブロックを順番に並べる」様子から「ブロックチェーン」と呼ばれるようになりました。ビットコインの生みの親であるサトシ・ナカモト氏が書いたホワイトペーパーには、「ブロックチェーン」という言葉はなく、「ブロックをつないでいるからブロックチェーン」というように、あとから共通認識になりました。
② P2P通信
「P2P(ピーツーピー)」は「Peer to Peer(ピア・ツー・ピア)」の略で、「Peer(ピア)」とは個人やコンピューターを指しており、P2P通信は対等の人や端末同士が直接通信をする方式のことです。
先ほどの図を再掲すると、色付きの部分がP2P通信です。クレジットカードや銀行などのような従来の送金システムとは異なり、当事者間に仲介業者が入ることなく、直接通信を行うことがP2P通信の特徴です。Peer間は仲介されることがなく、すべて対等で、上下関係などがないので、気を遣わずに取引ができます。第三者に手数料を取られることもありません。P2P通信のサービスとしてはファイル共有ソフトの「Winny(ウィニー)」などが有名です。
③ 分散型台帳技術(DLT)
分散型台帳技術は、データ(記録)を分散して管理する技術です。いきなり「分散」や「台帳」といわれてもピンとこないと思いますが、図にすると簡単です。
「ブロックチェーンの仕組み」の図の、ブロックをつないだ取引の部分を書き出したものが「台帳」で、その台帳をみんなで持つので「分散」です。つまり、「取引の記録をみんなで持ち、改ざんされていないかを互いにチェックしよう」という仕組みなのです。
分散型の台帳を持つみんなで取引の正しさを検証でき、誰かが自分の台帳を改ざんしても、ほかの誰かがその改ざんを検知できます。ビットコインの場合、この分散台帳を持っている人を「ノード」と呼び、このノードが多いほど「分散」していてネットワークの安全性が高いと評価されます。
ビットコインのノード数は「BITNODES(ビットノーズ)」で確認でき、2022年3月時点で1.5万台ほどあります。つまり、仮にビットコインをつぶしたい国や組織があっても、その国や組織は世界中に分散する1.5万台のノードを同時に破壊する必要があるということです。そんなことは現実的とはいえません。
また2021年6月までは、ノードの半数が中国に固まっており、地政学的なリスクがありましたが、中国が暗号資産の規制を強化し、事業者を国外に追放したことで、ビットコインの地理的分散性は高まりました。国の経済が破綻すると価値がなくなってしまう法定通貨と、世界中に分散する1.5万台のノードに守られたBTCと、どちらが信用に足るかは今後の歴史で証明されることでしょう。
④ コンセンサス・アルゴリズム
コンセンサス・アルゴリズムとは、コンセンサス(合意)形成を行うための仕組みやルールのことです。ここでの合意とは、「AさんからBさんへの送金記録をブロックに詰め、チェーンでつないでよいか」ということを指します。
ビットコインの場合、この合意をとるための仕組みはPoW(プルーフ・オブ・ワーク)と呼ばれます。ざっくりと説明すると、「稼働中のビットコインのノード群に難しい計算問題を出し、解けたらブロックチェーンに追加する」という仕組みです。このとき、一番早く問題を解いたノードに対し、報酬としてBTCが支払われます。この仕組みを「マイニング」といいます(マイニングの説明は後述します)。
難しく考える必要はなく、コンセンサス・アルゴリズムは「ブロックのつくり方」と考えておけば十分です。コンセンサス・アルゴリズムにはPoS(プルーフ・オブ・ステーク)などもありますが、次のように覚えておけば問題ありません。
PoW マイニングするコンピューターをたくさん持っているやつがえらい
PoS マイニングする通貨をたくさん持っているやつがえらい
それでは次に、ビットコインはブロックチェーン技術で「どんなルールを改ざんできないようにしているのか」を見ていきましょう。
4.ビットコインのマイニングと半減期
ルールとして設定されたもの
ビットコインにおいて「改ざんできないルール」として設定された重要なものは、次の3点です。
① BTCの発行枚数は2,100万枚
② BTCはマイニングによって発掘される
③ マ イニング量は4年に1度半減する(半減期がある)
このルールを書き込んだプログラムを、ブロックチェーン技術で改ざん不能にした「世界共通で不変のプロトコル」が機能することで、ビットコインを実現しています。①については、そういうものと覚えてください。BTCは2,100万枚あるのです。
BTC発掘のルールによる需要と供給の変化
BTCの発行枚数は2,100万枚で、一気に発行されたわけではなく、マイニングによって徐々に発行される仕組みになっています。最初はすべて埋まっており、マイニングで(つるはしで)掘り出す必要がある点は、金(ゴールド)と性質が似ています。
金が年間どれくらい発掘できるかは、そのときの世情などによって変わります。しかし、ビットコインはプロトコルによって年間の発掘量が正確に決まっており、最初の4年間で半分の1,050万枚、次の4年間でさらに半分の525万枚が発掘できるというルールです。この4年に1回、BTCの発掘量が半分になるタイミングを「半減期」と呼びます。このマイニングと半減期の仕組みにより、BTCの市場供給量は、次のような図で表現できます。
累計発行数(折れ線)は2,100万枚に限りなく近づきつつも、年間に供給されるBTCの発掘量(棒)は減少していく構造になっていることがわかると思います。BTCは2100年頃に掘り尽くされる計算ですが、すでに総供給量の90%が発掘され、残り10%を100年ほどかけて市場に供給していく計画になっています。
これはどういうことかというと、BTCの価値に気づく人はこれから多く出てくるので、BTCの「需要」は増加しますが、「供給」は残り10%しかなく、増えた需要が限られた供給を奪い合うという構図になります。希少で需要の高いものの価値が高まることは自明です。
半減期が来るとBTCの価格が上昇
このように、ビットコインの半減期が、BTCの価格を高騰させる要因になっています。
ビットコインのマイニングをする人のことを「マイナー」と呼びます。マイナーは、PoW(3. 改ざんできない仕組みを実現する技術 参照)でブロックを生成したときに支払われる、マイニング報酬のBTCを法定通貨に換金し、収益としています。マイナーの収益モデルを数式化すると、次のようになります。
収益={( BTC発掘の確率)-(電気代)-(マシンコスト) }×BTC価格
マイニングしたBTCを換金し、そこから電気代とマイニング用のマシンコストを差し引いた金額が収益です。これにより、一定量のBTCが売りに出されることになるので、BTC価格の高騰を妨げる「売り圧」となるのです。
マイナーがマイニングしたBTCは、常に売り圧として市場に供給されるので、BTC価格に蓋をする構造になっています。「売り圧に蓋」という表現がわかりにくいかもしれませんが、株式投資や暗号資産の取引における板取引をイメージしてください(次図左を参照)。板取引とは、「買い板」に買いたい人、「売り板」に売りたい人の希望価格を並べ、ちょうど真ん中の価格で取引をする形態のことです。
マイナーはマイニングしたBTCを売ることで収益を得ています。そのため、通常はマイナーが価格を上げようとしても、複数のマイナーが大量のBTCを売り板に並べるので、価格が上がりにくい構造になっています。しかし、ビットコインの半減期が来ると、マイナーの収益が半分、売られるBTCの量が半分になるので、価格に蓋をしていた売り圧も半減し、価格が上がりやすくなります。
2020年は、新型コロナウイルスの蔓延が投資市場に大きな影響を及ぼしましたが、ブロックチェーン市場で最も大きな影響となったのはビットコインの半減期でした。BTC価格が半減期により高騰することは予想されていたことです。これが4年に1度やってくることが、ビットコインのプロトコルに刻まれた不変のルールです。オリンピックのある年がビットコインの半減期にあたり、ビットコインが大好きなビットコイナーは4年に1度のこのイベントをオリンピック以上に楽しみにしています。
S2F(ストック・トゥ・ーフロー)モデルは、現在の備蓄量(ストック)と新規供給量(フロー)をもとに価格を予測するモデルであり、金や銀などの希少性の高い天然資源などの理論価格を導くためによく使われる指標です。このS2Fモデルは、金と性質の似ているビットコインにも適用できるとされており、BTCの理論価格の参考にされることが非常に多い指標です。次図がBTCのS2Fモデルです。

出典:Buy Bitcoin Worldwide「Bitcoin stock to flow model live chart」のWebページより
細い折れ線が理論価格、太い折れ線が実際のBTC価格、グラデーションで半減期のタイミングを示しています。チャートを見ると、周期的に価格が上昇していることがわかります。太い折れ線の丸を付けた箇所が半減期の開始時期なので、そこに注目すると、半減期のあとに価格が上昇する構造になっています。また現時点において、BTC価格は理論価格より安いことがわかります。
6.Web3.0プロトコルの成長サイクル
ビットコインの半減期により4年に1度、BTC価格が上昇することを説明しました。BTC価格が高騰すると、ニュースでは「暗号資産バブル」などと紹介されますが、そのニュースをきっかけにBTC購入者が増える正のサイクルが回り始め、需要が増える構造になっています。価格が上昇するとBTCに興味を持つ人が増え、そのなかから「なぜ?」と思う人が現れ、自ら調べてこれまで説明したような事実に気づき、ビットコインのファンが増えるサイクルになっています。もちろん、この気づきが早いほどBTCを安価で購入でき、投資のメリットも大きくなります。
✅まとめ✅
・ブロックチェーン市場の2兆ドルの市場規模はBTCが牽引して成長
・BTCの発行枚数は2,100万枚で、ブロックチェーン技術により供給量は固定
・BTCはマイニングで発掘され、発掘量はプログラムにより決まっている
・プログラムには半減期が設定されており、市場供給量は減少していく
・BTC価格はS2Fモデルに準拠し、半減期ごとに価値が上昇する見込み