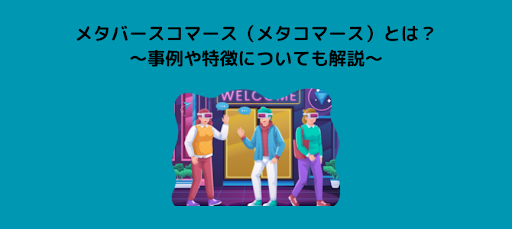メタバースコマース(メタコマース)とは

メタバースコマース(メタコマース)とは、仮想空間上で展開されているサービスを意味する「メタバース」と、電子商取引を意味する「Eコマース(Electric commerce)」という言葉を掛け合わせた造語です。
主にメタバースと呼ばれる仮想空間による商品の売買を総称してメタバースコマース(メタコマース)と呼ばれます。
それぞれの言葉に比べると聞き慣れない言葉ではありますが、両者の親和性が高く、ウェブ上でも店舗にいるような体験ができる場所として注目されています。
従来のようなECサイトによる販売だけでなく、Instagramを用いたSNS経由での商品販売や、オンラインミーティング機能を活用したウェブ接客など、広いチャネルで活用されています。
そもそもメタバースとは
メタバースとは、一般的に仮想空間を指します。メタバースの定義には諸説ありますが、超越を意味する「メタ(meta)」と、宇宙や万物を意味する「ユニバース(universe)」を掛け合わせた造語です。
すでにゲームやイベントが仮想空間で行われており、NFTを組み合わせたアイテムの展開や、Meta社(旧Facebook社)の立ち上げたMeta Horizon Workroomsなどのサービスが行われており、市場でも盛り上がりを見せています。
メタバースとVRやARとの違い
メタバースはARやVRなどと混同されやすい概念です。
VRとは
VRは、「バーチャルリアリティ(Virtual Reality)」の略称で仮想現実の意味を持ちます。仮想空間を通じて現実に居るかのような体験が可能な技術やサービスを意味することが多いです。ARと比べて、没入感が強く、よりクローズドな世界観を楽しむことができるでしょう。
ARとは
一方で、ARは「アーグメンテッドリアリティ(Augmented Reality)」の略称で、拡張現実とも表現されます。スマートフォンなどを通じて実在する景色に、バーチャル的な視覚情報を重ねる技術を意味します。VRに比べると手軽な反面、あくまでも現実世界の拡張・延長という印象が強いです。
メタバースとVRの違い
メタバースとVRは、没入感の強さなど同じように感じますが、厳密には異なる概念です。自分だけでも楽しめるVRに対して、メタバースは他人とのコミュニケーションを目的としています。
-
アバターが使用できる
-
参加できる人数が多い
-
自由に世界を構築できる
など、一定の要件を満たしてこそのメタバースです。
メタバースコマース(メタコマース)が市場に与える影響について

メタバースコマース(メタコマース)は、市場においてどのような影響を与えるのでしょうか?
市場に与える影響1. イベントや広告の変化
メタバースコマースが普及することで、ユーザーがオンライン上で過ごす時間が増えていきます。それに伴い、従来行われていたイベントが、メタバース上で行われることが増えると予想されます。
また、ライブイベントやスポーツなどを仮想空間で楽しむ時代が訪れるとともに、企業は広告収入のシェア争いが加熱していくでしょう。
市場に与える影響2. バーチャル商品の販売が可能になる
メタバースが普及してくと、仮想空間における自分(アバター)に着せるアイテムなども需要が高まってきます。
その際に、アバターに着せるための服やアイテムなどを扱うことで、新しい路線で商品の販売を行うことが可能です。バーチャル商品であれば、在庫数などの管理も必要なく、生産するためのラインも必要ありません。
すでに、メタバース内のアバター用にNFTアイテムが販売された事例もあり、今後も広く盛り上がっていくと予想がされます。
メタバースコマース(メタコマース)のメリット

では、メタバースコマースにおけるメリットについても見ていきます。
メタバースコマース(メタコマース)のメリット1. コストの削減
現実世界にお店を出す際は、土地代や光熱費に人件費、さらに人員の確保...と、金銭面でもそれ以外でも多くのコストがかかります。
実店舗はまだまだニーズがあるものの、大幅なコストカットが可能なメタバースコマースが当たり前の世界になる可能性もそう遠くないかもしれません。
メタバースコマース(メタコマース)のメリット2. 新規顧客の開拓
従来の感覚をもってすれば当たり前ですが、実店舗はそこに行かなければ商品の売買やサービスを受けることができません。
一方で、誰もが繋がることのできるウェブ上で店舗を構えることで、物理的な距離を無視して接客を行うことが可能です。
すでにオンラインショッピングが普及しているものの、実店舗感といったアバターによって接客を受けたり、スタッフとやり取りを行うという部分が従来のオンラインショッピングにはない強みになるのではないでしょうか。
メタバースコマース(メタコマース)のデメリット

ここからは、メタバースコマースにおけるデメリットについても見ていきます。
メタバースコマース(メタコマース)のデメリット1. ユーザビリティの悪さ
先ほどは、「アバターなどを通した接客体験などが、従来のECサイトにはない強みになる」とお伝えしました。
しかしこの手間こそが、ユーザーからすると面倒と感じてしまう恐れもあります。
今まで通り、「サイトにアクセスして欲しいものをカゴに入れて決済すれば終わり」で良かった買い物が、わざわざメタバースに入ってアバターを通じたやり取りなどの手間が増えることで、ユーザビリティの悪さがデメリットになる恐れがあります。
メタバースコマース(メタコマース)のデメリット2. 環境整備が追いついていない
この記事を執筆している2023年2月現在では、メタバースを楽しむためには環境の整備が整っていないと感じます。
一般的に理想とされる没入感を楽しむためには、VRヘッドマウントなど、大掛かりな機材が必要になり、手軽に楽しむためには価格も安くありません。
まずは、メタバースそのものが一般ユーザーに普及しないことには、メタバースコマースの良さを訴求することも難しいでしょう。
メタバースコマース(メタコマース)の事例紹介

最後に、メタバースコマースを実現した企業の事例を紹介します。
メタバースコマース(メタコマース)の事例1. BEAMS(ビームス)
幅広い年齢層に支持されるアパレルブランドのBEAMSは、2021年のバーチャルマーケット2021と呼ばれるイベントに参加し、アバターを用いた接客や商品の売買を行いました。
メタバースの中で洋服を試着したり、商品を手に取ってみるなどのバーチャル体験を提供し、進化を恐れない古豪アパレルブランドとしての存在感を示しました。
今後の取り組みにも目が離せません。
メタバースコマース(メタコマース)の事例2. NIKE(ナイキ)
世界的なスポーツブランドとして有名なナイキも2021年11月に、ロブロックスとよばれるゲームプラットフォーム内にショールームをオープンしました。
ショールームでは人気のスニーカーモデルが並んでおり、アバターが試着して楽しめる空間作りを演出しています。
ナイキは、2021年にバーチャルスニーカーブランドの「アーティファクト」を買収したことで、NFTの世界にも広く展開を進めており、今後もさらに勢いを増していく見込みです。
メタバースコマース(メタコマース)の事例3. Burberry(バーバリー)
王室御用達のトレンチコートで有名な英国のアパレルブランド、バーバリーも2021年に銀座店をベースにしたバーチャルポップアップをスタートさせました。
これまで紹介してきた「メタバース内」という概念ではないものの、メタバースコマースのという言葉の本質的な意図に近いため取り上げておきます。
わかりやすくお伝えすると、GoogleマップのストリートビューのようなUIで、バーバリーの店舗内を自由に動くことができます。マークのついている商品をクリックすることで商品の値段や画像が表示され、興味があれば商品詳細ページへリンク・購入ができるというものです。
ウェブ上ではあるものの、実店舗で買い物をする楽しさや、綺麗にレイアウトされた商品の中から選ぶ楽しさなどが感じられ、従来のオンラインショッピングの一歩先を行く体験でした。
メタバースコマース(メタコマース)を活用して次世代の商品販売チャネルを

メタバースコマースは、メタバース上にて従来のECサイトやオンラインショッピングにはない体験を提供する場として、近年注目を浴びているサービスでした。
メタバースコマースを用いることで、手軽に店舗で買い物をする楽しさや喜びだけでなく、販売する商品のコストカットにも繋がり、サステナブルな面でも大いに期待がされています。
SUSHITOPMARKETINGでは「メタバース店舗」というメタコマースが可能なサービスを提供しています。
興味のある方はぜひ関連ページをご覧ください!